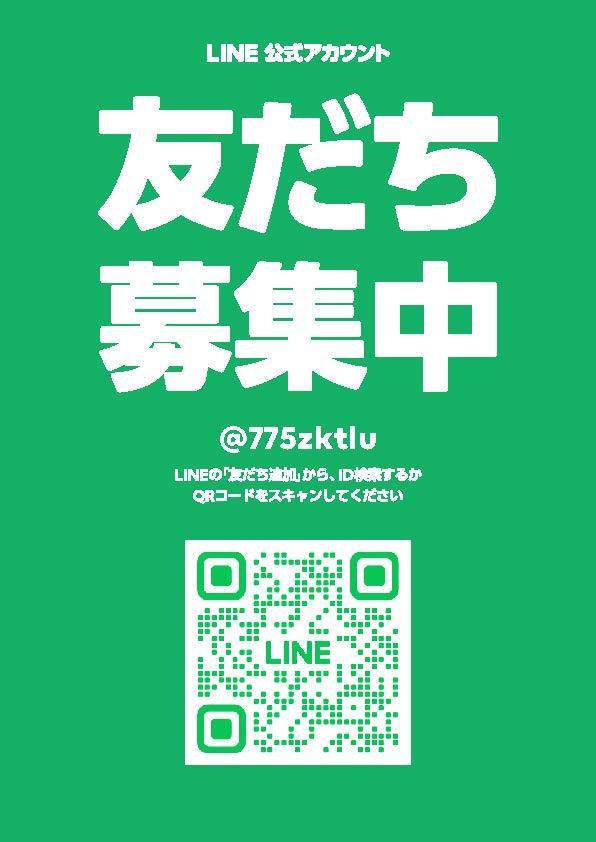投稿日:2025年12月20日(土)
絶滅のおそれのある野生動植物が、国際取引によってさらに減少することを防ぐための国際条約です。

目的
規制の仕組み(附属書)
対象となる動植物は、危険度に応じて3つに分類されます。
ユーザー様が関わる水産・食品輸入では特に重要です。
ワシントン条約(CITES)附属書Ⅰ〜Ⅲの違いは?
附属書Ⅰ(Appendix I)
絶滅の恐れ:非常に高い
[ 原則 ]国際商業取引 ✖ 完全禁止
特徴
ゴリラ、トラ、ジャイアントパンダ
附属書Ⅱ(Appendix II)
絶滅の恐れ:中(管理が必要)
[ 原則 ]国際取引 ○ 可能 → ただし「許可制」で厳格管理
特徴:
ラン・サボテン類
ヨロパウナギ
チョウザメ(キャビア)
サメ類(フカヒレ)
附属書Ⅲ(Appendix III)
絶滅の恐れ:比較的低い(特定国が保護)
[ 原則 ]取引 ○ 可能 → 指定国からの輸出のみ管理
特徴
一部木材・動物種
ワニ類(特定国)
| 項目 | 附属書Ⅰ | 附属書Ⅱ | 附属書Ⅲ |
|---|---|---|---|
| 絶滅リスク | 非常に高い | 中 | 低 |
| 商業取引 | ❌ 原則不可 | ⭕ 管理下で可 | ⭕ 可 |
| 主な書類 | 輸出+輸入許可 | 輸出許可 | 輸出許可 or 原産地証明 |
| 実務頻度 | 低 | 非常に高い | 低〜中 |

実務ポイント(重要)
投稿日:2025年3月15日(土)
うなぎは日本の食文化に欠かせない存在ですが、その供給を支える重要な漁法のひとつに「シラス漁」があります。シラス漁は、うなぎの稚魚である「シラスウナギ」を捕獲するための漁で、主に冬から春にかけて行われます。本記事では、シラス漁の仕組みや課題、そして持続可能なうなぎ漁への取り組みについて詳しく解説します。
シラスウナギとは、うなぎの稚魚のことで、透明で体長は約5〜6cmほどです。大人のうなぎと違い、まだ体色がなく、細長いガラス状の姿をしています。シラスウナギは、太平洋のマリアナ諸島付近で孵化し、黒潮に乗って日本の河口へとたどり着きます。この時期のシラスウナギを捕獲し、養殖場で育てることで市場に出荷されるのです。
シラス漁は、主に河口や沿岸部で行われます。漁の方法としては、夜間に光を利用してシラスウナギを集め、専用の網で捕獲する「光漁法」が一般的です。具体的な手順は以下の通りです。
シラス漁は非常に繊細な作業であり、漁獲量が年によって大きく変動するため、漁師にとっては一か八かの大きな賭けとも言えます。
近年、シラスウナギの漁獲量は減少傾向にあります。これは、主に以下のような要因が影響しています。
このままでは、将来的に天然のうなぎが絶滅する可能性もあるため、資源保護が急務となっています。
うなぎの資源を守るために、日本国内ではさまざまな取り組みが進められています。
養殖場や市場において、正規のルートで仕入れたシラスウナギかどうかの管理体制を強化。
漁獲制限の導入
各都道府県ごとにシラスウナギの漁獲量を制限し、過剰な捕獲を防ぐ動きが強まっています。
捕獲期間の制限(12月〜4月の限定期間のみ漁獲)などのルールも設けられています。
養殖技術の向上
現在の養殖業はシラスウナギを捕獲して育てる「半養殖」が主流ですが、近年では完全養殖(人工ふ化から成魚まで育成)が研究されています。
完全養殖が普及すれば、天然のシラスウナギに依存しない生産が可能になります。
密漁・違法取引の取り締まり強化
違法な漁獲や不正流通を防ぐため、取り締まりが厳しくなっています。
シラス漁は、日本のうなぎ文化を支える重要な産業ですが、資源の減少が深刻な問題となっています。環境変化や乱獲によって漁獲量が減少する中、持続可能な漁業の実現が求められています。今後、シラスウナギの資源管理を徹底し、完全養殖の技術開発を進めることで、未来の世代にも美味しいうなぎを届けられるよう努力していく必要があります。
うなぎを楽しむためにも、私たち消費者も持続可能な取り組みに関心を持ち、環境に配慮した選択をしていきましょう。
ちなみに2025年はシラス豊漁です。

投稿日:2025年3月15日(土)
日本において「うなぎ」は、長い歴史を持つ食材のひとつです。特に「土用の丑の日」に食べる習慣が広く知られていますが、その背景にはどのような歴史があるのでしょうか?また、うなぎの持つ栄養価と健康効果についても詳しく掘り下げてみましょう。

うなぎが日本で食されるようになったのは、奈良時代(8世紀)頃とされています。当時の貴族たちは、滋養強壮の食材としてうなぎを好んで食べていました。平安時代の『延喜式』には、宮廷の食材としてうなぎが記録されており、すでに貴重な食べ物として認識されていたことが分かります。
江戸時代に入ると、うなぎの蒲焼きが庶民にも広まりました。醤油やみりんといった調味料が普及したことにより、現代に通じる「たれ」を使った蒲焼きが登場し、屋台などでも手軽に食べられるようになりました。また、江戸時代中期の学者・平賀源内の働きかけによって、「土用の丑の日にうなぎを食べる」習慣が定着したといわれています。
土用の丑の日とは、五行思想に基づいて季節の変わり目にあたる「土用」期間のうち、十二支の「丑の日」にあたる日を指します。この時期は特に暑さが厳しく、体力が消耗しやすいため、栄養価の高いうなぎを食べることで夏バテを防ごうとする風習が生まれました。
また、「丑の日に『う』のつく食べ物を食べると良い」という言い伝えがあり、うなぎのほかにも「梅干し」や「うどん」などが推奨される食材とされていました。
うなぎは、非常に栄養価の高い食材であり、健康維持や疲労回復に役立ちます。
これらの栄養素が豊富に含まれているため、特に夏場の疲れやすい時期には理想的な食材と言えます。
日本各地には、独自のうなぎ料理のスタイルがあります。
これらの違いも、日本各地の食文化を感じられるポイントのひとつです。
近年、天然のうなぎ資源が減少し続けており、養殖うなぎの需要が高まっています。養殖技術の発展により、安定的な供給が可能となっていますが、資源保護の観点からも持続可能な消費を考える必要があります。環境に配慮した養殖方法や代替食材の研究が進められており、今後のうなぎ食文化の未来にも注目が集まっています。
うなぎは日本の食文化に深く根付いた食材であり、古くから滋養強壮に優れた食品として愛されてきました。土用の丑の日に食べる習慣も、健康を考えた先人たちの知恵のひとつと言えます。ただし、資源の保護や持続可能な消費も重要な課題となっているため、環境にも配慮しながら、伝統の味を楽しんでいくことが求められます。今年の夏も、栄養たっぷりのうなぎを味わいながら、日本の食文化を再認識してみてはいかがでしょうか?

LINE
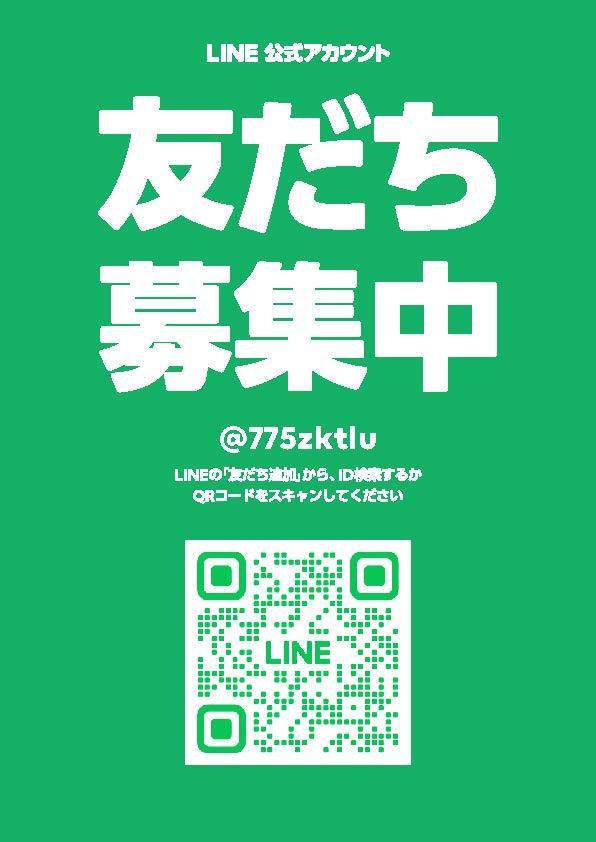
投稿日:2025年3月15日(土)
「土用の丑の日」と聞くと、多くの人が「うなぎ」を思い浮かべるのではないでしょうか?毎年夏になると話題に上るこの日は、日本の伝統的な風習の一つであり、季節の変わり目を意識した文化が根付いています。今回は、土用の丑の日の由来や意味、そしてうなぎを食べる風習について詳しくご紹介します。
「土用」とは、四季の変わり目にあたる約18日間の期間を指します。古代中国の五行思想に基づき、春は「木」、夏は「火」、秋は「金」、冬は「水」に分類され、それぞれの季節の終わりには「土」の気が強くなるとされました。この「土」の期間が「土用」です。
土用は春夏秋冬それぞれにありますが、特に夏の土用が広く知られています。それは、夏の土用が梅雨明けの時期と重なり、最も暑さが厳しくなる頃だからです。

「丑の日」とは、十二支の「丑(うし)」にあたる日のことです。十二支は、子(ね)、丑(うし)、寅(とら)……と12種類あり、日にちにも割り当てられています。そのため、土用の期間内に「丑の日」が巡ってくると「土用の丑の日」となります。
毎年、土用の丑の日は異なり、年によっては一度だけの年もあれば、「一の丑」「二の丑」と2回ある年もあります。
土用の丑の日にうなぎを食べる習慣は、江戸時代の学者・平賀源内(ひらがげんない)が広めたと言われています。当時、夏場にうなぎの売れ行きが悪くなったため、あるうなぎ屋が平賀源内に相談しました。そこで源内は「本日、土用の丑の日」という看板を店頭に掲げることを提案しました。これが評判を呼び、他のうなぎ屋も同様の宣伝を行うようになり、次第にこの風習が定着していったとされています。
また、五行思想では「丑の日に『う』のつく食べ物を食べると夏バテしない」という考えもあります。うなぎのほかにも、梅干し、うどん、瓜(スイカやキュウリ)なども良いとされています。

うなぎは、ビタミンAやB群、D、Eが豊富に含まれた栄養価の高い食材です。特に、ビタミンB1は疲労回復に効果的で、夏バテ防止に役立ちます。また、EPAやDHAといった不飽和脂肪酸も含まれており、健康にも良い影響を与えます。
土用の丑の日は、五行思想に基づく季節の変わり目の行事であり、うなぎを食べる風習は江戸時代から続くものです。栄養満点のうなぎを食べて、暑い夏を元気に乗り切りましょう。うなぎ以外にも「う」のつく食べ物を取り入れて、夏バテ対策をするのも良いかもしれません。今年の土用の丑の日には、ぜひ家族や友人と美味しい食事を楽しんでみてはいかがでしょうか?
当社自社ECショップのご案内 UNASOAKGO