
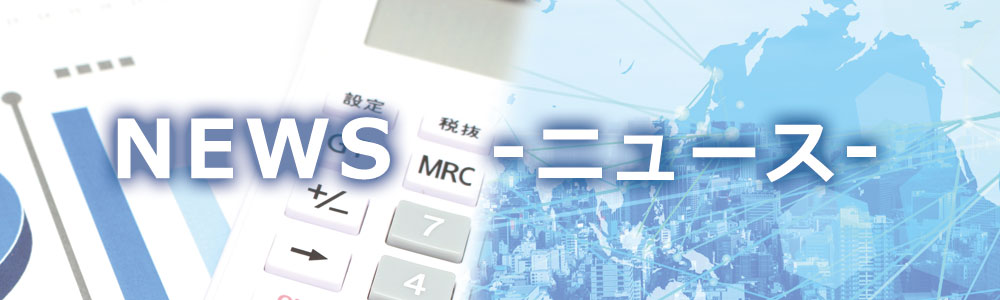
投稿日:2025年3月15日(土)
鰻のシラス漁とは?
うなぎは日本の食文化に欠かせない存在ですが、その供給を支える重要な漁法のひとつに「シラス漁」があります。シラス漁は、うなぎの稚魚である「シラスウナギ」を捕獲するための漁で、主に冬から春にかけて行われます。本記事では、シラス漁の仕組みや課題、そして持続可能なうなぎ漁への取り組みについて詳しく解説します。
シラスウナギとは、うなぎの稚魚のことで、透明で体長は約5〜6cmほどです。大人のうなぎと違い、まだ体色がなく、細長いガラス状の姿をしています。シラスウナギは、太平洋のマリアナ諸島付近で孵化し、黒潮に乗って日本の河口へとたどり着きます。この時期のシラスウナギを捕獲し、養殖場で育てることで市場に出荷されるのです。
シラス漁は、主に河口や沿岸部で行われます。漁の方法としては、夜間に光を利用してシラスウナギを集め、専用の網で捕獲する「光漁法」が一般的です。具体的な手順は以下の通りです。
シラス漁は非常に繊細な作業であり、漁獲量が年によって大きく変動するため、漁師にとっては一か八かの大きな賭けとも言えます。
近年、シラスウナギの漁獲量は減少傾向にあります。これは、主に以下のような要因が影響しています。
このままでは、将来的に天然のうなぎが絶滅する可能性もあるため、資源保護が急務となっています。
うなぎの資源を守るために、日本国内ではさまざまな取り組みが進められています。
養殖場や市場において、正規のルートで仕入れたシラスウナギかどうかの管理体制を強化。
漁獲制限の導入
各都道府県ごとにシラスウナギの漁獲量を制限し、過剰な捕獲を防ぐ動きが強まっています。
捕獲期間の制限(12月〜4月の限定期間のみ漁獲)などのルールも設けられています。
養殖技術の向上
現在の養殖業はシラスウナギを捕獲して育てる「半養殖」が主流ですが、近年では完全養殖(人工ふ化から成魚まで育成)が研究されています。
完全養殖が普及すれば、天然のシラスウナギに依存しない生産が可能になります。
密漁・違法取引の取り締まり強化
違法な漁獲や不正流通を防ぐため、取り締まりが厳しくなっています。
シラス漁は、日本のうなぎ文化を支える重要な産業ですが、資源の減少が深刻な問題となっています。環境変化や乱獲によって漁獲量が減少する中、持続可能な漁業の実現が求められています。今後、シラスウナギの資源管理を徹底し、完全養殖の技術開発を進めることで、未来の世代にも美味しいうなぎを届けられるよう努力していく必要があります。
うなぎを楽しむためにも、私たち消費者も持続可能な取り組みに関心を持ち、環境に配慮した選択をしていきましょう。
ちなみに2025年はシラス豊漁です。
