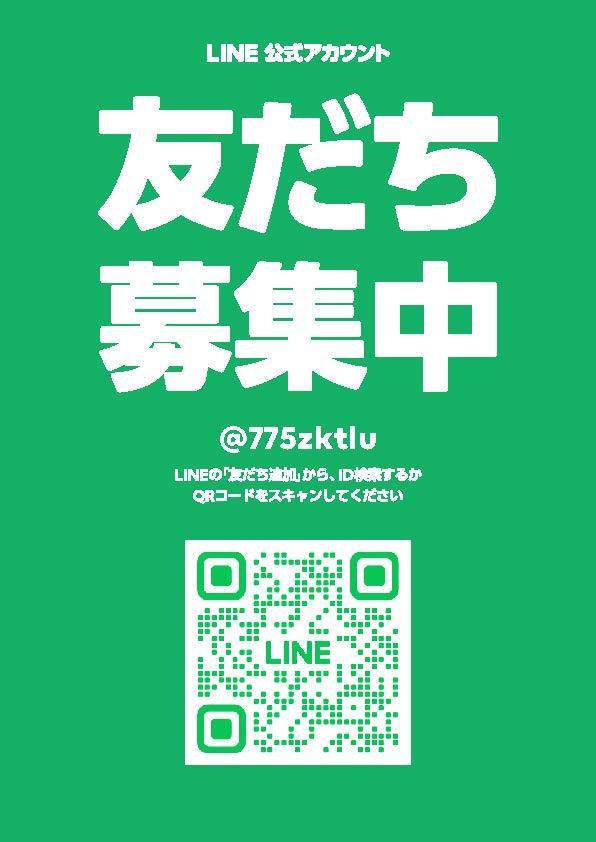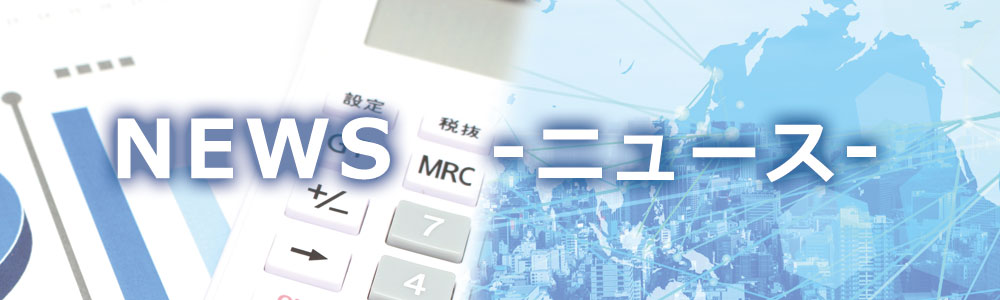
投稿日:2025年3月15日(土)
土用の丑の日とは?
「土用の丑の日」と聞くと、多くの人が「うなぎ」を思い浮かべるのではないでしょうか?毎年夏になると話題に上るこの日は、日本の伝統的な風習の一つであり、季節の変わり目を意識した文化が根付いています。今回は、土用の丑の日の由来や意味、そしてうなぎを食べる風習について詳しくご紹介します。
「土用」とは、四季の変わり目にあたる約18日間の期間を指します。古代中国の五行思想に基づき、春は「木」、夏は「火」、秋は「金」、冬は「水」に分類され、それぞれの季節の終わりには「土」の気が強くなるとされました。この「土」の期間が「土用」です。
土用は春夏秋冬それぞれにありますが、特に夏の土用が広く知られています。それは、夏の土用が梅雨明けの時期と重なり、最も暑さが厳しくなる頃だからです。

「丑の日」とは、十二支の「丑(うし)」にあたる日のことです。十二支は、子(ね)、丑(うし)、寅(とら)……と12種類あり、日にちにも割り当てられています。そのため、土用の期間内に「丑の日」が巡ってくると「土用の丑の日」となります。
毎年、土用の丑の日は異なり、年によっては一度だけの年もあれば、「一の丑」「二の丑」と2回ある年もあります。
土用の丑の日にうなぎを食べる習慣は、江戸時代の学者・平賀源内(ひらがげんない)が広めたと言われています。当時、夏場にうなぎの売れ行きが悪くなったため、あるうなぎ屋が平賀源内に相談しました。そこで源内は「本日、土用の丑の日」という看板を店頭に掲げることを提案しました。これが評判を呼び、他のうなぎ屋も同様の宣伝を行うようになり、次第にこの風習が定着していったとされています。
また、五行思想では「丑の日に『う』のつく食べ物を食べると夏バテしない」という考えもあります。うなぎのほかにも、梅干し、うどん、瓜(スイカやキュウリ)なども良いとされています。

うなぎは、ビタミンAやB群、D、Eが豊富に含まれた栄養価の高い食材です。特に、ビタミンB1は疲労回復に効果的で、夏バテ防止に役立ちます。また、EPAやDHAといった不飽和脂肪酸も含まれており、健康にも良い影響を与えます。
土用の丑の日は、五行思想に基づく季節の変わり目の行事であり、うなぎを食べる風習は江戸時代から続くものです。栄養満点のうなぎを食べて、暑い夏を元気に乗り切りましょう。うなぎ以外にも「う」のつく食べ物を取り入れて、夏バテ対策をするのも良いかもしれません。今年の土用の丑の日には、ぜひ家族や友人と美味しい食事を楽しんでみてはいかがでしょうか?
当社自社ECショップのご案内 UNASOAKGO